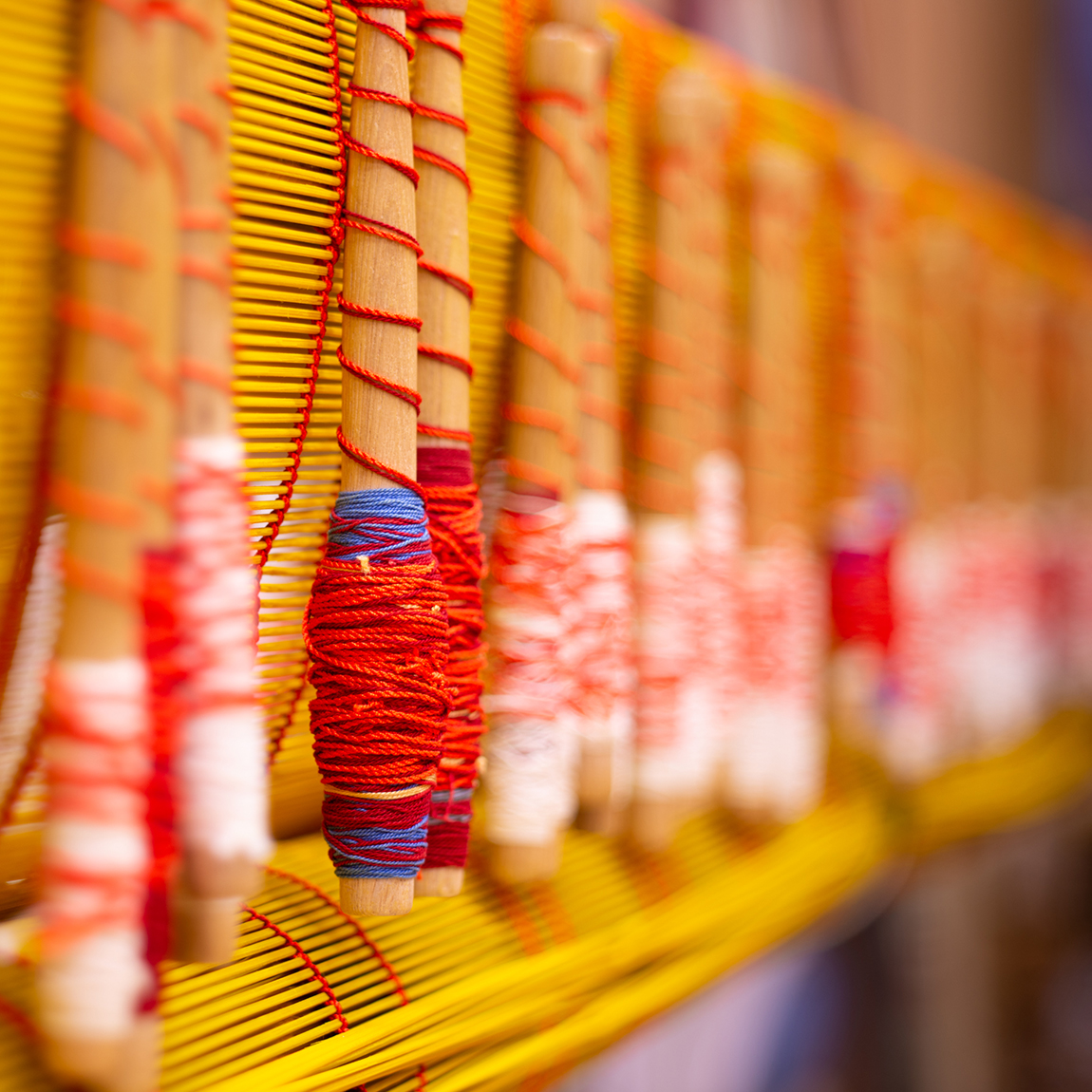十五世豊斎作 茶盌紅鹿背唐人笛(写真提供:朝日焼)
父との別れ
後日、佑典さんは葬儀のときの気持ちをこのように話してくれた。
「それまでのこと、これからのことで頭がいっぱいで。父はあの窯焚きの後、亡くなるひと月前にもう一度窯焚きに臨みました。ことあるごとに『最後の窯焚きや』と話していましたが、僕自身は『まだまだいけるだろう』と、どこか安心していたんですよね。結果的に(その窯焚きが)父の言った通りになったんですが、こちらは心の準備なんてできていませんから」
約400年続く朝日焼の十五世、豊斎さんの死は世間から大きな注目を集めた。そして、近く佑典さんが継承するであろう十六世のあり方にも。
しかし、彼らは師弟である前に親子だ。
代々窯元を継ぐ家だからといって、当代の死と同時に特別なことが起きるわけではない。そこには、誰もがそうであるように、肉親を失った家族の悲しみがあるだけだ。

「どこにでもある家族の話です。家族の死に直面して思いを巡らせ、また日常に戻って懸命に仕事や生活を続けていく。もちろん父が培ってきた作陶とその精神性は引き継いでいくのですが、それが『継承』という大それたものなのかは、正直なところまだわかりません。故人の思いを大切にすることも、家族としてごく当たり前のことですから」
新しい豊斎
約半年後の2016年6月11日。平等院浄土院で佑典さんの十六世襲名式がおこなわれた。父の葬儀があったこの場所で、佑典さんは父と祖父と同じ「豊斎」の名を継いだ。
これから襲名後の各展覧会に向けた作品制作や、関係各所への挨拶回りなど慌ただしい日々が続く。悲しみにくれる間もなく、朝日焼の日常は動き出していた。
2016年10月、佑典さんが十六世を襲名してからはじめての窯焚きがおこなわれた。窯出しを終えたばかりの佑典さんは、重責から解放された安心感からか、少し体調を崩していた。
「新しい課題をひとつずつ確認するような窯焚きでした。おかげさまで窯焚きは無事に終えましたが、今回は窯に詰める前までの制作がまず大変で。父の作品と比べていかに『自分らしさ』を表現するかを考えましたが、そもそもそういう悩みにとらわれること自体が朝日焼らしくないとも思いましたしね。結局は今の自分にできることを精一杯やろう、と自分なりに挑戦もできました」
今回の窯焚きは、社会から「新しい豊斎」のあり方を問われる第一歩でもある。
「豊斎を名乗るようになって、『佑典』の頃とは脱皮した姿を見せなくてはいけないと思うようになりましたが、それが簡単じゃないこともわかっているつもりです。父の生前には無意識に避けていた作風もありますので、今後もチャレンジが続きます。父は朝日焼の『重し』だったんだなとつくづく思いますよ」
これまでは、先代が窯の伝統的な作風を守ることで、佑典さんがより挑戦的な陶芸に向き合うことができた。今後は、その両面を佑典さんが担っていくことになる。

佑典作 茶盌月白釉流し(写真提供:朝日焼)
「ようやく父がろくろ場にいないことに慣れてきました。悲しいというか、なんだか寂しい感じですね。いつもそばにあるものが無い違和感というか。でも、こうして父がいない風景が当たり前になっていくのでしょう」
なんでもないようなもんで、良いもん
「なんでもないようなもんで、良いもんを作らなあかん」
佑典さんは、先代がよく口にしていた言葉を思い出す。
「良い物」の定義は曖昧で、それが茶事の構成要素のひとつである茶器ならなおさらだ。茶室に溶け込んで、手に馴染み、派手さはなくとも存在感がある器。言葉にするのは容易だが、それはいったいどのような器なのか。
「僕の場合は『朝日焼らしさ』が正しさの指標になるのだと思います。父や祖父、そして歴代の作はどれも違った特徴があるけど、並べて見るとどれもが朝日焼らしい。父の言葉は『平凡だけど、凡庸じゃない』という意味だと解釈していますが、こんなに難しいことはないですよね。今にして思えば、父も祖父の作品を見て同じようなことを考えていたのでしょう」
代を継ぐ、ということ
先代、豊斎さんが亡くなる3ヶ月前、佑典さん夫婦に長男が誕生した。豊斎さんにとっては初孫だった。筆者が取材した折にも、この話題になると豊斎さんは「楽しみなもんやね」と目を細めていた。
「最後に孫に会わせてあげられて本当によかった。欲を言えば、子供に祖父の記憶を残してあげたかったけど少し時間が足りなかった。この子が将来、朝日焼を継ぐのかはわかりません。僕も父から仕事を継げと言われたことはありませんでしたし、親子といえど、人に言われて始める仕事でもないと思っていますから」(佑典さん)
朝日焼(松林家)の家訓には、次のような一文がある。
「伝統は守るものでなく、攻めるものである」
朝日焼が宇治に窯を開いてから約400年。その歴史を紐解くと、安定よりも困難な時期の方が長い。茶陶の家を維持し、満足ゆく器を焼き続けるためには、変化を恐れずに歩む心構えを説いた家訓なのだろう。
「この1年、これほど継承ということについて考えた時期はなかった。『父との最後の窯焚き』『父の死』『長男の誕生』と本当にいろんなことがありましたから。代を継ぐとはどういうことか、いくら考えてもまだ答えは出ません。でも、焦ってはいないんですよ。僕が次の代に朝日焼を引き渡すまでに答えを見つけていくものなんだと思っています。たぶん、父もそうして考え続けていたんでしょうね」

朝日焼では、宇治で採掘した陶土を約10年ほど寝かせて使う。年月をかけて風雨にさらすことで、土は熟成し、まるで生き物のように含有成分が変化する。それが窯の炎と相まって「窯変」と呼ばれる色彩や模様を生むのだ。
陶土は50年前、100年前のものも保管されており、ときにはそれらを混ぜ合わせて使うこともある。絵付けを施さない朝日焼にとってさまざまに熟成した陶土は唯一の材料であり、何にも代えがたい財産なのだ。
「ずっと宇治の土だけを使ってきた。そこに、同じ場所で作陶を続ける大きな意味があるんやろね。代々、父や祖父が掘った土を使い、息子や孫のために土を掘ってきた。うちはそれを400年間続けてきたんやから。いろんな作風があっても、どれも『朝日焼らしさ』があるのはそのためちゃうかな」
生前、そう話していた十五代豊斎さんの言葉を思い出す。
これからしばらく、佑典さんは先代が用意した陶土を使うのだろう。そして、先代と同様に次の世代のために土を掘り続けるはずだ。
当たり前のことを、毎日、粛々と。
先人と同じ日々の積み重ねが、かたちなき伝統をつくり、それこそが朝日焼にとっての「継承」なのだろう。

かたちなき「伝統」。朝日焼の継承にまつわる(ごく一部の)物語|[1]|[2]
朝日焼
京都府宇治市宇治山田11番地
http://www.asahiyaki.com/
SPECIAL
TEXT BY YUJI YONEHARA
PHOTOGRAPHS BY YUJI YONEHARA
17.01.07 SAT 23:34