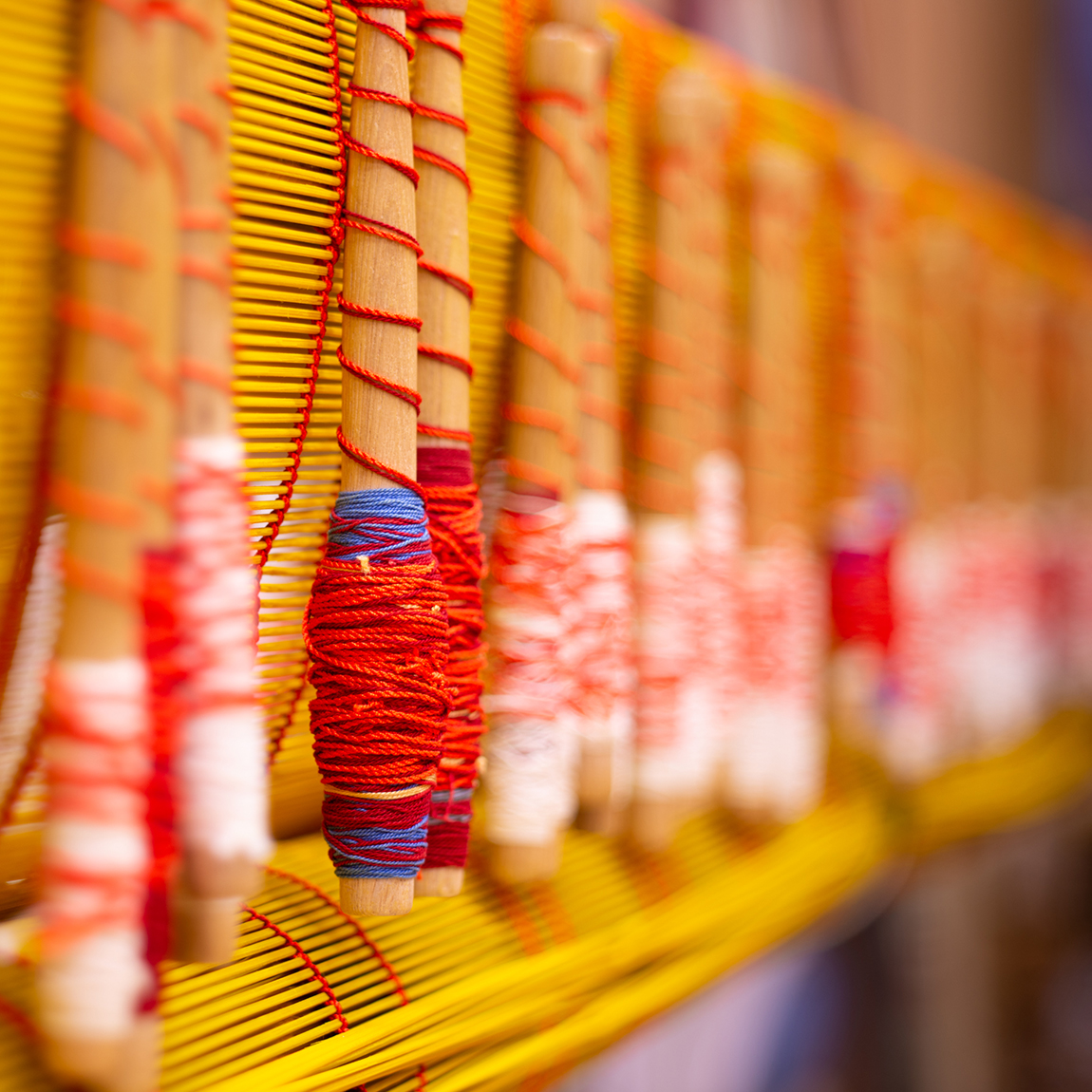「一、八瀬に窯を開く」全景

主屋の居間の間取りをもとにした上がり間

石黒宗麿《柿釉水指》1955年頃/石黒宗麿《番茶器》1936年頃
長年使っていた土鍋が割れた。いつものようにコンロに火をかけて水炊きを準備していると、鍋の底から出汁が吹きこぼれた。かれこれ十数年前に「僕には大きいから」と恩師から譲り受けた越前焼の土鍋である。鍋の蓋には鉄絵で大きくカニが描かれている。鍋底を洗うたびに貫入が深まっていくのに見惚れていた。ところが、鍋底にひびが入りはじめた。たたいてみると、鈍い音がした。お粥を炊いてそのひびを埋めようとしたけれども、もう手遅れだった。陶片の断面は黒く焦げ付き、土の中から出てきたものに見えた。
石黒宗麿(1893-1968)は、1936年から75歳で歿するまでの33年間を京都洛北の八瀬で過ごした。主屋は、茅葺きの寄棟作りで、土間、居間、水廻りという簡素な間取りである。10畳ほどの土間が仕事場である。石黒は日本、朝鮮、中国といった東洋古陶磁に自らの陶器作りのルーツを見出し、その再現を試みていた。「膝の片方に小山先生から貰った出土陶片、もう片方に出来上がったばかりの碗を載せ「出来た、出来た」と、奥さんと抱き合って喜んでおられました」という清水卯一(1926-2004)の証言が残されている(小野公久『評伝 石黒宗麿 異端に徹す』淡交社、2014年)。この「出土陶片」とは、当時親交を深めていた陶磁研究家・陶芸家である小山冨士夫(1900-1975)から譲り受けた北宋時代の磁州窯の陶片と思われる。中国の河北省南部の邯鄲市鉅鹿(かんたんしきょろく)は、1108年に黄河の大洪水によって沈んだ町である。1920年の干ばつの時に深く井戸を掘ったところ、多くの陶片が出土した。磁州窯は庶民の生活雑器であり、白化粧した素地に黒泥を掛け、黒泥のみを掻き落とす技法が見られる。石黒はそのなかでも「千点文」と呼ばれる模様の再現を試みた。そして、その模様がロクロのおどりによってリズミカル刻まれていることを突き止め、弾力の強いカンナ(時計のぜんまいを伸ばしたもの)を用いて削ることで再現して見せたのである。
石黒は古陶磁の「写物屋」として語られがちである。ただ、若かりし八木一夫(1918-1979)はそれだけではないことを気づいていた。八木は、1947年頃に青年作陶家集団の仲間と連れ立って八瀬に石黒を訪ねている。「そのときの私は、石黒さんの仕事の裏うちとなっているはずの、「古典」という古色の型を感じたりはしなかった。むしろ、作家個人だけにとどまらず、現代そのものにも生きている感覚や、瀟洒な好み、造りのたしかさと柔軟性、そんなものに感心させられていたという記憶がある」と記している(八木一夫『懐中の風景』講談社、1967年)。石黒は磁州窯の技法をもとに千点文の茶碗や鉢、蓋物を作り出したが、釉薬、形、模様は独自のものである。八木は1948年に走泥社を結成し、オブジェ焼へと進んでいくが、晩年に作った千点文の湯呑みには、石黒と通底した古典に対する解釈を見出すことができる。
石黒が八瀬で暮らしていた当時の写真をみていると、土間の囲炉裏には、茣蓙が敷かれ、鉄瓶に湯が沸かされている。囲炉裏の炉縁は、レンガの寸法をもとにしたやきもので組まれ、上面と側面には淡い緑釉が施されている。炉縁が破損した箇所は、石黒の陶器と思われる数個の陶片で補修されている。そのうちの一箇所には、白化粧で象嵌された魚紋の陶片が埋め込まれている。目玉が二つ並んで、囲炉裏で焼かれたアジの開きのように見えてくる。

「二、石黒宗麿の陶器作り」全景

登り窯近くから掘り起こされて石黒宗麿の陶片

来場者は陶片に触れることができる

石黒宗麿の陶器と八瀬陶窯の生活のスライドショー
このようないくつかの石黒の陶片にまつわる振る舞いをもとに、本展の会場構成を考えた。なにより登り窯の近くから大量に掘り起こされた陶片に触れることを展示の見どころにした。一部屋目は「八瀬に窯を開く」とし、主屋の居間と同じく十畳半の上がり間を設え、石黒の陶器とそれに類する陶片を並べた。履物を脱いで畳に上がり、手のひらのなかで陶片に触れて見比べる。たとえば、柿釉の水指は落ち着いた渋みのある肌であるのに対して、並べられた陶片は光沢感が強くその違いが見て取れる。二部屋目は「石黒宗麿の陶器作り」とし、400点余りの陶片を作業台の上に並べ、その陶器作りのバリエーションを俯瞰する構成とした。そして、三部屋目は「五〇年目の窯出し」とし、今回の調査で登り窯の二の間から発見された木葉天目茶碗がどのような環境で作られたのかを窯道具や登り窯の模型を通してみていく構成とした。匣鉢(さや)のなかからでてきた茶碗にはまだ目土がくっついている。
石黒にとって古陶磁の陶片は写し取るものであり、他方で自作の陶片は、埋めるべきものだったのかもしれない。だから50年ぶりに掘り起こされた陶片は、石黒の陶器とは似て非なる出土品のように見えるのである。

「三、五〇年目の窯出し」全景

八瀬陶窯の登り窯模型とそのフロッタージュ

登り窯の二の間から発見された木葉天目茶
石黒宗麿
1893(明治26)年、富山県射水郡作道村(現射水市)に医者の長男として生まれる。25歳の頃に見た曜変天目茶碗の美しさに感銘を受け陶芸家を志す。東京、埼玉、金沢と転居しながら作陶を続け、1927(昭和2)年に京都市東山区に居を移す。天目釉を中心に東洋古陶磁のさまざまな技法研究に取り組んだが特定の師にはつかず、古陶磁を教材として製陶研究に勤しんだ。1936(昭和11)年には京都市左京区八瀬に築窯した住居兼工房である「八瀬陶窯」で作陶を始める。1955(昭和30)年、鉄釉陶器の技法で重要無形文化財保持者(人間国宝)認定を受けた。1956(昭和31)年に八瀬陶窯を財団法人化し、後進の陶芸家養成の拠点づくりをめざした。

1983年東京生まれ、京都在住。2011年京都精華大学芸術研究科博士後期課程修了。博士(芸術)。京都精華大学芸術学部造形学科特任講師。〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイルなどの学術研究と作品制作を行なう。最近の展示に「六本木クロッシング2013:アウト・オブ・ダウト―来たるべき風景のために」(森美術館、2013年)、「第8回アジア・パシフィック・トリエンナーレ」(クイーンズランド・アートギャラリー、2015年)、「第20回シドニー・ビエンナーレ」(キャレッジワークス、2016年)、「あいちトリエンナーレ2016」(愛知県美術館、2016年)、「東アジア文化都市2017京都」(京都芸術センター、2017年)など。
会期 2018年12月14日(金)-2019年1月12日(土)
会場 京都精華大学ギャラリーフロール
主催 京都精華大学
協力 射水市新湊博物館/銀座 黒田陶苑/金田正夫(有限会社無垢里)/木立雅朗(立命館大学)/黒石いずみ(青山学院大学)/坂部真理(株式会社環境事業計画研究所)/田畑幸嗣(早稲田大学)/ナワビ矢麻(早稲田大学)/余語琢磨(早稲田大学) 企画 京都精華大学 八瀬陶窯研究会(米原有二/奥村博美/斎藤光/兼松佳宏/中村裕太) 実行委員会 小野公久/木村盛伸/黒田佳雄/鯉江良二/清水保孝/馬場弘吉/原清/森口邦彦
URL:https://www.kyoto-seika.ac.jp/fleur/past/2018/1214ishiguro/index.php
REPORT
TEXT BY YUTA NAKAMURA
PHOTOGRAPHS BY NOBUTADA OMOTE
19.03.01 FRI 18:22